


[ハルト]「耳障りだ。私語は慎め」
[リート]「ご、ごめんなさい」
[アルシェ]「いいじゃん、ハルト。 そんな堅苦しい挨拶なんかしなくたって。
彼女、怖がっちゃってるよー。ねぇ?」
アルシェさんは華のような笑顔で、私の前へ。
そして、お辞儀をするような姿勢で私の手を取る。
[アルシェ]「こんにちは、可愛らしいお嬢さん」
まるで貴族かお姫様になったかのような扱いに、照れくささを隠せない。
顔が熱くなっているのが自分でもわかる。
[アルシェ]「俺──君とは、初めましてじゃないよね」
[リート]「え……は、はい。 あの、この間の公演で……」
[アルシェ]「ああ、やっぱり。 入口で白いエリカの花束をくれた子だよね。
覚えてるよ」
[アルシェ]「名前は、確か、キャサリン」
[リート]「……リート、です」
[アルシェ]「あはは、あれ。そうだっけ。 まぁいいか。
これから、もっと仲良くなろうね」
[アルシェ]「白いエリカの花言葉は『幸せな愛を』」
[リート]「……」
アルシェさんはそういって、ごく自然に手の甲へキスをした 。
一瞬何が起こったかわからなかったけれど、
状況を理解すると、恥ずかしさで顔がさらに熱くなるのを感じた。

[ハルト]「──おい」
[ハルト]「今、オルガンを弾いていたのは──
お前だな」
ハルトさんが厳しい眼差しを私に向ける。
綺麗な瞳だけれど……
にらみつけるような目線は冷たく、
怖い、と感じてしまう。
[リート]「は、はいっ。
はじめまして、私──」
挨拶の握手をするつもりで手を差し出しても、
ハルトさんは見向きもしない。
[ハルト]「酷く醜い音だった」
[リート]「──」
[ペーター]「なッ……」
みんなが不安そうな顔をしてハルトさんと私を
見つめていた。
言い返したいのに、
何を言っていいのか分からない。
確かに私の演奏はつたない。
それは自分でもわかっている。
だからこそ、
ハルトさんの言葉は私の胸をえぐった
[ハルト]「久し振りに、最低な演奏を聞いた」

[クラヴィア]「よかった。
今日は音が控えめだったので、
心配していたんですよ」
[リート]「え?
音って……私の、ですか?」
[クラヴィア]「ええ、いつもでしたら、
ものすごい派手な音を立てて、
ドアを開けて、やって来て……」
[クラヴィア]「弾んだ足音に飛び交う笑い声、
そして壮絶なボケツッコミの嵐が大音量で……」
[リート]「す、すみません、
うるさくしてしまって……」
[クラヴィア]「いいえ、私は、
ここであなたの音を聞くのが楽しみなんです。
足音、笑い声……それから」
[クラヴィア]「日替わりの鼻歌もね」
クラヴィアさんの微笑みは、
いつものように優しく穏やかだ。
彼の声を聞くと
気持ちが柔らかく解けていく気がする。

[ディー]「だーから俺は関係者じゃねーっつの。
まとわりつくな!」
[ペーター]「おい、クララ……いい加減にしとけって。
ねーちゃんの前に警備員が飛んでくるぞ」
[クララ]「だって私見たんだもん、
この人が劇場の楽屋口から入ろうとするところ!」
[クララ]「 関係者のクセに客を無視するなんて、
ひどいじゃない?」
[クララ]「ハルト様ほどの素晴らしい才能を持っている御方
ならともかくさー」
[ペーター]「だからっ
この人も演奏家の一人かもしれないだろ?」
[クララ]「ノー。絶対、ありえないわ。
見たことないし、知らないし」
[クララ]「そもそもオーラを感じないもの」
その言葉で何かスイッチが入ったのか、
青筋を立てながら、彼はにっこりと笑う。
[ディー]「……ふ。 よーし」
[ディー]「歯ぁ食い縛れメスガキ!
オーラどころか五感の全てを感じないように
してやらぁ! ぁあん!?」
[ペーター]「怖! つーか大人気な!
絶対楽団の関係者じゃないよこの人!?」



[ハルト]「楽器に触れても、音は応えない。
コンダクターとして指揮棒を振るっても、俺には……何も……」
[ハルト]「何も、産みだせない」
[リート]「そ、そんなこと、ありませんッッッ!」
[ハルト]「……」
[リート]「ハ……ハルトさんは、ハルトさんだから、
みんな、信頼して、
自分の音を預けているんです……!」
[リート]「わ、私は音楽のことは何もわからないけど、
でも……」
[リート]「これだけは、分かります。
音楽が、人を拒絶するなんてことない!」
[ハルト]「リート……」
[ハルト]「うるさい。声が大きいぞ。
子供達が、起きる」
[リート]「あ、ご、ごめんなさい……」
[リート]「でも──」
[ハルト]「……俺は、音楽に嫌われてもいい。
演奏が出来なくても、やるべきことはある」
[ハルト]「……俺が……」
[ハルト]「──誰よりも音楽を愛していれば、それでいい」
[リート]「……」
[リート]「……ハルトさん……」
[リート]「あの、もう一度、弾いてもらえませんか」
[ハルト]「?」
[リート]「私、聞きたいんです」
[ハルト]「……」
ハルトさんは戸惑いながらも、
ゆっくりとオルガンに手を伸ばす。
そして、そっと鍵盤に指をおく。
やはり音は出ない。
私はそれでもよかった。
[リート]「もう一度」
[ハルト]「……」
[リート]「お願いします」
ハルトさんは演奏を続ける。
オルガンから音は聞こえてこない。
私はそれでも、
ハルトさんの演奏を聞き続ける。

[ハルト]「リート」
突然、ハルトさんが私を抱きしめる。
あまりに突然過ぎて、頭がパニックになりかける。
ハルトさんらしくないような。
[ハルト]「……公演は、必ず、成功させる」
[ハルト]「これから、何が、起ころうとも……」
ハルトさんが言葉を切る。
声音は苦しげで、痛々しかった。
今まで笑っていたのに、楽しそうだったのに、
どうしてそんな声で……?
[リート]「ハルトさん、だいじょ……」
私の言葉をさえぎるように、ギュッと強く、
強く抱きしめられる。
[リート](ハルトさん……震えている……?)
私はハルトさんの背中に手を回した。
そしてゆっくり、優しく撫でる。
[リート](ハルトさん……私がついてますから……。
大丈夫ですよ……)
少しでもハルトさんが苦しくなくなるように。
[ハルト]「……」
しばらくそうしていると、ハルトさんの震えが
やっと治まった。
[リート]「大丈夫ですか?」
[ハルト]「ああ」
ハルトさんの手が緩まる。
私から身体を離す時、私の頬にかすかに
唇が触れる。
[リート]「ひゃっ」
驚いて変な声が出た。
ハルトさんがクスリと笑う。
でもすぐに真剣な表情で私の顔を覗き込む。
[ハルト]「何があっても、俺を信じてくれ……リート」

[ハルト]「だから、ずっと……お前のことばかり、
考えていた」
[リート]「……」
[ハルト]「だが……
……
……もう、やめた」
[リート]「え。や、やめちゃったんですか?」
[ハルト]「ああ。
二度と考えないことにする」
[リート]「あ、や、やっぱり嫌われちゃってる……」
[ハルト]「俺は、お前に嫌われてもいい」
[リート]「え──」
[ハルト]「……俺が……」
[ハルト]「──誰よりもお前を愛していれば、それでいい」
[リート]「……っ!」
この言葉は……。
[リート]「ハルト、さん……」
[リート]「あ、あの。
でも、それだと、
私と同じになっちゃいませんか?」
[リート]「私も、その、ハルトさんに、
片思い……しているんです」
[ハルト]「ああ、そうだったな」
[リート]「私は、振られたと思っているんですけど。
でも、今の話は、つまり、あれ……?」
[ハルト]「だから、俺は、お前の気持ちは、
もうどうでもいいと言っている」
[ハルト]「俺が、お前のことを、好きなんだ」

[リート]「……本当に、ごめんなさい」
アルシェさんに、頭を下げる。
[アルシェ]「何が?」
[リート]「私のせいで、
たくさん……ご迷惑をおかけしてしまって」
[リート]「一歩間違えれば、皆さんの音も……
消えてしまうかもしれなかった……」
[アルシェ]「……じゃあ、まさかとは思うけど、
その時の、罪滅ぼしを、
こんなことでしているつもり?」
[リート]「あ……」
たじろぐ私を見て、
アルシェさんが大きなため息をつく。
[アルシェ]「はぁ……」
呆れたような様子に、
思わず居住まいを正す。
何か気に障ってしまっただろうか。
[アルシェ]「なっちゃんさ」
[リート]「──」
[リート](怒られる……ッ!)
そう思って、思わず目を閉じてしまった。
[アルシェ]「じいしきかじょーすぎ」
[リート]「きゃ」
予想外の言葉と共に、
鼻の頭をちょん、と押された。
思わず、小さな悲鳴が漏れる。
[アルシェ]「なっちゃんは
舞台に上がりたくても上がれない子なんだから」
[アルシェ]「そんな、悲劇のヒロインみたいなこと
言わなくていーの」
[アルシェ]「全然似合ってないよ?」
[リート]「……」
[リート](言い方は悪いけど、もしかして……
励まそうとしてくれてる、のかな?)

アルシェさんの瞳をじっと見つめる。
澄んだ緑色の瞳が、微かに揺れた気がした。
[アルシェ]「ここにいたって……期待していることなんか、
何ひとつ起こらないよ」
[アルシェ]「俺、君のこと、別に好きじゃないもん」
[リート]「はい」
[アルシェ]「ってゆーか、ハッキリ言ってすっごい迷惑」
[リート]「はい」
[アルシェ]「出てけよ」
[リート]「いやです」
アルシェさんから告げられるのは、明確な拒絶。
それでも、私はひくつもりはなかった。
互いの目を見つめ合ったまま、しばしの沈黙が流れる
[アルシェ]「……
……
……変態」
ため息交じりにそう呟くと、アルシェさんは立ち上がり、私の両手を乱暴に掴んだ。
[リート]「ッ」
[アルシェ]「じゃあなに、
ハルトがなっちゃんに教えたダンスの責任は、
俺が取らなきゃいけないの?」
[アルシェ]「……勘弁してよ」
強い力で抱き寄せられた。
顔も体も触れてしまうほど近く、
一気に心音が激しさを増す。
戸惑う私をよそに、
強引にステップを踏み始める。
八つ当たりのように激しいステップに、
私はただ振り回されるだけだ。
アルシェさんと踊ろうと思って、
必死に覚えたステップ。
なんとかついていこうと、必死で体を動かした。
[アルシェ]「上手だね」
[リート]「……」
[アルシェ]「俺の為に、頑張ってくれたんだ。
でも──」
アルシェさんは急にステップを止めると、
両手で強く私を抱きしめる。
ふわりと微かに甘い香りが舞った。
[アルシェ]「俺は心が無いから、誰も好きにならないし、
誰がいなくなったって、
何にも感じない」
[アルシェ]「『ここ』から
動けない」
[リート]「……え」
[アルシェ]「おとぎ話に出て来る王子様、みたいでしょ?」

[リート]「でも、アルシェさん……
本当に良かったんですか?」
[アルシェ]「なにが?」
[アルシェ]「演奏は何処でも出来るけど、
リートはここにしかいないでしょ」
[リート]「え」
唐突に、
アルシェさんの唇が、私の唇に触れた。
あまりに突然のことで、
数秒間、私の思考回路は完全にフリーズする。
[リート]「えぇぇぇぇぇっ!?」
状況を把握してから、
慌ててアルシェさんから離れようとする。
[アルシェ]「ダメ、死んでも離してあげない」
[リート]「あ、アルシェさん──」
[アルシェ]「俺、誰のことも、好きにならないから」
[アルシェ]「浮気とかいっぱいしちゃうけど」
[アルシェ]「それでもいい?」
[リート]「え──、い……」
[リート]「嫌です」
[アルシェ]「え」
[リート]「だ、だって……浮気されたら、嫌です」
[アルシェ]「いや、今のは、
だから、冗談──でもないけど」
[リート]「ま、またそうやって私のこと、からかって!
私、アルシェさん──苦手です!」
[リート]「か、か、帰りますッッッ!」
[アルシェ]「ちょ、ちょっ──ちょっと待ってよ、
リートッッッ!?」

目を覚ました私は、
ベッドの中で大きなあくびをした。
ぼんやりと辺りを見渡すと、
ソプラノの姿が見えないことに気づく。
[リート]「あれ、ソプラノ?」
いや、それよりも、
見慣れない景色に、徐々に眠気が覚めていく。
[リート]「っていうか、ここ──私の部屋じゃな──」
ハッとして隣を見ると、誰かが寝ている。
すやすやと気持ち良さそうに
寝息を立てているのは——
[ヴィッセ]「……すぅ……」
[リート]「なんッッッ──」
ヴィッセの姿に、大声を上げそうになる。
口を押さえてなんとかこらえると、
ヴィッセが身じろぎをした。
[ヴィッセ]「ん……」
白いシーツの上に広がったヴィッセの髪が、
彼の寝息で小さく揺れた。
ぴくりと動く長いまつげに、
ドキドキとしながら息を潜める。
[ヴィッセ]「すぅ……」
ヴィッセが起きないのを確認すると、
ほっと肩の力を抜いた。
[リート]「そっか、私……
昨日、あのまま寝ちゃったんだ……」
時計を見るとすっかり朝。
どうやら、一晩寝てしまっていたらしい。
[リート]「新しい年、かぁ……」
[リート]「今年もよろしくね。
ヴィッセ……」
ヴィッセの頭を撫でようと手を伸ばす。
なんて綺麗な寝顔だろう。
もし天使がいるとしたら、こんな顔を
しているんじゃないだろうか。
白い肌に、指が触れる寸前——
[リート]「……じゃなくて!
お、起きなきゃっ!
私、何やってるんだろう」
慌てて手を引くと、
立ち上がるため身を起こそうとする。
けれど……。
[リート]「……う、動けない……」
ヴィッセにしっかりと抱きしめられていて、
身動きがとれなかった。
[リート]「……」
[リート]「あったかい……」
もぞもぞと布団に潜り込み、
そっとヴィッセの身体に手を回してみる。
[リート]「ヴィッセって、意外と体温高いんだな……」
[リート]「……もうちょっとだけ……」
心地よい誘惑にかられ、私はもう一度目を閉じた。

[ヴィッセ]「っしょ……」
おそるおそる木に登っていくヴィッセを、
ハラハラとしながら見守った。
赤ちゃんとその母親も、
心配げにヴィッセを見上げている。
[リート]「慌てず慎重にね、ヴィッセ
落ちて怪我なんてしたら、ピアノが——」
[ヴィッセ]「わかってる
——あ」
こちらを向いた瞬間、
細い枝がヴィッセの頬を掠めた。
ヴィッセの頬に薄く赤い筋が入った。
[リート]「ヴィッセ──」
[ヴィッセ]「……大丈夫。 もう、ちょっ、と──」
枝に身を乗り出すようにして、
ヴィッセが風船に手を伸ばす。
もう少しで手が届くところで——
パトカーのサイレンが響いた。
その音に驚いたヴィッセの身体がビクッと揺れた。
[リート]「あ……ッ」
風によって傾いた風船は、
枝に刺さってあっけなく割れてしまった。
[ヴィッセ]「あ──」
[赤ん坊]「あ……
ぅ、わあああああああああああんッッッ!」
呆然とするヴィッセの眼下で、
赤ちゃんが大きな泣き声を上げる。
[ヴィッセ]「あ、ご、ごめ……」
慌てて謝ろうとするヴィッセだが、
泣き声に遮られて赤ちゃんには届いていない。
[母親]「あの……ありがとうございます。
お気持ちだけで、充分ですので……」
母親は、私と木の上のヴィッセに頭を下げると、
赤ちゃんを乳母車に乗せて去っていく。
[母親]「よしよし。
おうちに帰って、おやつ食べようねぇ」
[母親]「その前に手を洗おうねぇ。
ぱしゃぱしゃねー」
[赤ん坊]「あううー」
赤ちゃんは最後まで、悲しそうな声を上げていた。
[ヴィッセ]「……」
[リート]「……」
哀し気な瞳で親子を見送るヴィッセに、
何も声をかけられず、
私はただ木を見上げる。
[ヴィッセ]「……」
[ヴィッセ]「……って言うか、これ、
……どうやって、降りればいいんだろう……」
[リート]「え」
[ヴィッセ]「ど、どうしよう俺……」
[ヴィッセ]「このままじゃ……!」
急に慌て出すヴィッセに、
私までわたわたしてしまう。
[リート]「ヴィ、ヴィッセ、とにかく、落ち着いて!」
[ヴィッセ]「う、うん。」
[ヴィッセ]「……すぅ。
……はぁ」
ヴィッセは深呼吸すると、
何かを決意したように、頷いた。
[ヴィッセ]「よし。
一生をここで、過ごすよ」
[リート]「落ち着いちゃダメーーー!」
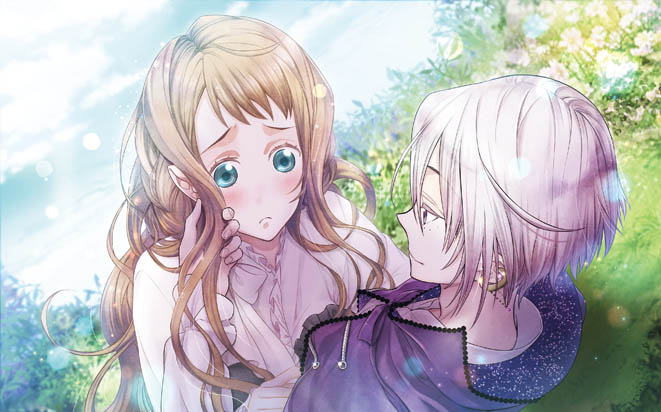
[ヴィッセ]「……ぷ。あははははっ」
[リート]「ヴィッセ……?」
[ヴィッセ]「だって、鼻、赤くなってる」
[リート]「え、う、嘘ッ!?」
そう言われて、私は思わず鼻の頭を隠した。
[ヴィッセ]「そんなことしたって意味ないよ」
[ヴィッセ]「俺よりリートの方が手当、必要かも」
[リート]「へ、平気だもん……」
[ヴィッセ]「……真っ赤だよ」
[リート]「平気なのっ」
[ヴィッセ]「本当に?
痛く、ない?」
ヴィッセが私の顔に手を伸ばす。
その指先は、赤くなった鼻先ではなく髪に触れる。
[ヴィッセ]「あ……髪、さらさら、ふわふわ。
気持ちいいね」
[ヴィッセ]「もう少し、触っていても、いい?」
ヴィッセの指先で髪をもてあそばれ、
すごく照れくさい気持ちなってしまう。
良く考えると、この体勢は……。
体が密着していて、目の前にヴィッセの顔がある。
それを意識してしまってから、
顔は熱くなる一方だった。
[ヴィッセ]「……よしよし」
[リート]「ヴィ、ヴィッセ、怪我したの鼻だよ。
髪じゃ、ないよ」
[ヴィッセ]「いいこだねー」
[リート](う、なんだかすごく恥ずかしい。
とにかく、髪から手を放してもらおう)
ヴィッセの手を払おうとすると……。
[ヴィッセ]「あはは、やっと鼻から手を放した。
隠しちゃうんだもん。
引っかかったー」
[リート]「……え」
そういって、
ヴィッセは私の鼻をまじまじと見つめる。
[ヴィッセ]「ん……ちょっと、赤くなっているけど、
大丈夫そう。
大したこと無くてよかった」
[ヴィッセ]「でもほら、よかったじゃん。
鼻が一番高いってことが、分かって」
[リート]「ぜ、全然よくないよ!
ヴィッセの意地悪!」
[ヴィッセ]「じゃあ、トナカイみたいな赤鼻を記念して、
一枚」
[リート]「と、撮っちゃダメだってばー!」
真っ赤な鼻の記念写真を残したくないので、
再び手で顔を隠そうとした。
[ヴィッセ]「ダメ。隠したら」
[リート]「……」
[ヴィッセ]「ダメ」
[リート]「……もう……」
本当は顔を隠したかったけれど、
ヴィッセにそんな顔をされたら、もう……。
ヴィッセは優しく微笑んでいる。
私も気を取り直して、ヴィッセに笑った。
[リート]「ね。ヴィッセ。
みんな、すごく楽しそうだったね」
[ヴィッセ]「え」
[リート]「私も楽しい。
みんなとこたつに入ったり、お絵かきしたり」
[ヴィッセ]「楽しい……」
[ヴィッセ]「……そっか」
私がヴィッセに微笑むと、
ヴィッセも笑って……、
穏やかな時間に目を細める。
大事な思い出を取りこぼさないように、
私達は写真を撮った。

ヴィッセの話を聞いていると、
気付かない内に私の目から、大粒の涙が零れていた。
[ヴィッセ]「……リート?」
[リート]「ごめんなさい……
でも、そんなの……悲しいよ」
[リート]「だって、ヴィッセは、何も──」
[ヴィッセ]「君は……優しいね」
ヴィッセは私の頬を伝う涙を指で優しく拭う。
そして、その指は頬、首筋へ。
ヴィッセは、優しくなだめるように、
私の頬や首をなでてくれた。
ヴィッセに触れられた部分だけ、
やけに熱く感じる。
[リート]「ヴィ、ヴィッセ……」
[ヴィッセ]「ん?」
[リート]「あの、……
なんか、これだと……」
[ヴィッセ]「……ペットみたい?」
[ヴィッセ]「ん、じゃあ、これで」
ヴィッセは私を抱き寄せると、頭を撫でる。
[ヴィッセ]「よしよし、いい子だね……」
[リート]「ヴィッセ……」
[ヴィッセ]「……いいんだよ……笑って」
[リート]「……」
[ヴィッセ]「君は、何にも、悪くないんだから……」
[リート]「うん……」
それはきっと、小さい頃ヴィッセ自身が
お母さんに言って欲しかった言葉なのだろう。
[リート]「ヴィッセ……」
私はヴィッセをそっと、抱きしめる。
暖かく包み込むように、そっと、優しく。
[リート]「上手だよ……
よく、出来ました」
[ヴィッセ]「うん……」

[ルドルフ]「しかし
かろうじて、数字らしき部分は、
読み取れる……」
[ルドルフ]「そこから推察するに、
1、2というのは……日付。
1900は、時刻を表していると、僕は考える」
[ルドルフ]「つまり、今日の午後7時に……何かが起こる、と」
[ディー]「んで、最後の22……。
ああ、これがコイツの名前ってぇことか?」
[アントン]「まぁ、ぶっちゃけ、これが予告状なのかも、
差出人が怪盗なのも、
俺達には分からないんですけどね」
[ルドルフ]「だが、犯人は、この手紙をシャル市警宛てに
送りつけてきた。それは間違い無い」
[ルドルフ]「つまり、
何らかの犯行予告と考えるのが自然だろう」
[ルドルフ]「実に難易度の高い──巧妙なやり口」
[ルドルフ]「警察の上層部は、音楽と関係の無い事件は
後回しにしろと言うが、 僕はそんなことは思わない」
[ルドルフ]「この手紙を見過ごすことで、
不幸になる住民がいるかもしれない──
それは、僕の正義に反する」
[ディー]「確かに。
何か起きてからじゃ、遅いな」
[ルドルフ]「ああ」
[ディー]「だからって、この時間の無い中、
シャル中の猫好きに職質かけまくるって方法は
どうかと思うぜ?」
[ディー]「ったく、お前は、
昔っからバカ正直なんだからよ……」
[ディー]「だから俺にも、すぐ騙されるんだ」
[ルドルフ]「だから、僕はバカじゃないと何度言ったら──」
[ディー]「ま、そのおかげで?
お前といると、ちっとも、飽きねぇけどな」
[ルドルフ]「ディー……!」
ルドルフさんは、再びだーっと涙を流した。
やっぱりディー君のこと好きなんだね。
[アントン]「ちなみに、現役悪戯っ子から見て、
この事件──どう思います?」
[ディー]「そうだな。
もし本当に、この事件に何かしら『猫』の存在が
絡んでるってんなら……」

[ディー]「よし、帰ろうぜ」
[リート]「えっ」
[ディー]「つーか逃げるぞ!
とっととさっさと一目散にッ!」
[リート]「ディー君よかったやっと分かってくれて
とっととさっさと大賛成ッ!」
[ディー]「おぅ、珍しくノリが良いな! 行くぞ!」
[リート]「うん!」
私は勢いよく頷いて、ディー君に向かって手を差し出した。
[ディー]「……は?」
[リート]「は、じゃないでしょ、早く!
行こう!」
せかすと、ディー君は困ったような顔をしながら、
そっと私に手を伸ばした。
[ディー]「あー、うん。そ、そうだな……」
[ディー]「お前は別に俺と手を繋ぐという意識はなく、
そこに手があるから繋ぐ、山があるから登る、
本当にただそれだけの行為ということなんだよなこれは」
[リート]「……?
ごちゃごちゃうるさいよ、ディー君」
[ディー]「なッ……」
[リート]「ほらっ」
ディー君の手を強引に握ると、
なぜか彼はかぁっと頬を赤くした。
ディー君の手を引いて、駆け出す。
[ルドルフ]「っ、あーーーーー!
ディー、待ちたまえッッッ!」
[ルドルフ]「君にはいろいろと聞きたいことが──」
[ディー]「ヤベぇ、バレたバレたッ」
ディー君が、足を速めると、
ぐっと手を引かれる形になる。
ディー君は、
きらきらと目を輝かせて笑顔で走る。
その様子を見て、思わず笑ってしまった。
[リート](ディー君はまだまだ演奏よりも、悪戯かな……?)
けれど、ディー君なら、
クラヴィアさんの期待に応え、
立派に演奏もやり遂げてくれる――そんな気がした。
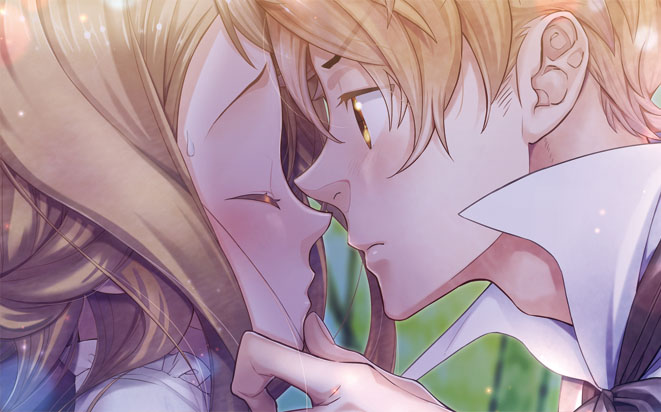
[ディー]「よぉし、目を瞑れー。
今から苦く苦しいお茶の時間のはじまりだー!」
[リート]「うぅう……」
[リート](ディー君に悪戯しようなんて、
思うんじゃなかった)
観念して、目を瞑った。
けれど――
[リート]「……?」
しばらく目を瞑っていても、何も起こらなかった。
室内が静まり返り、首を傾げる。
[リート]「ディー、君? どうしたの?」
目は開けずに、ディー君の返事を待った。
少ししてから、ディー君がぽつりと呟く。
[ディー]「お前……
意外と、まつげ、長いんだな」
[リート]「へッ!?」
そっと目尻に触れられ、びくっと肩が跳ねた。
[リート]「な、ななな」
[リート](触られた!?)
[ディー]「ここ……
赤くなってる」
今度は、ディー君の指が耳に触れる。
思わずぱちっと目を開けた。
[リート]「ちょっと、ディー君、何を――」
[リート](あ……)
ディー君の真剣な瞳が、
まっすぐ私を見つめていた。
その色素の薄い瞳に、
吸い込まれるように目が逸らせなくなる。
[ディー]「嫌だったら、逃げろ。
そうじゃ、ないなら……俺と──」
ディー君の顔が、近づいてきて――

[ヴィッセ]「うん。
クラヴィアは楽団のおかーさんだからね」
[アルシェ]「じゃーおとーさんはハルトってこと?
俺、やだなぁ、ハルトの息子になるの」
[クラヴィア]「大丈夫ですよ。演奏におけるハルトの奥さんは、
アルシェ、あなたですから」
[アルシェ]「いや、そういうことじゃないから……
俺、別にそこに何も嫉妬してないからッ!」
[ヴィッセ]「ねぇクラヴィア、猫の里親のことなんだけど……」
[クラヴィア]「ああ、そうですね……そろそろ、
引き取り先を探さないといけませんね。
母猫の具合は、どうですか?」
[ヴィッセ]「うん、やっぱりちょっと、元気ないみたい……」
[クラヴィア]「そうですか。でも、心配はいりません。
今はヴィッセの側で、
ゆっくり休ませてあげてください」
アルシェさんとヴィッセに取り囲まれ、
クラヴィアさんは柔らかく微笑んだ。
クラヴィアさんの周りには、
いつも彼の助言を求める人がたくさん集まって来る。
クラヴィアさんはそれを静かに聞き入れ、応える。
言葉で、時には行動で。
[ビアンカ]「あ、いけない。
私もクラヴィアさんに確認してもらわなきゃいけないことあったんだった」
[ビアンカ]「しかし、
また見事に捕まっちゃってるわぁ……」
[リート]「クラヴィアさんの周りには、
いつもたくさん人がいますね」
[ビアンカ]「んーそうねぇ。相談に乗ってくれたり、
話を聞いてくれたりするから……自ずとみんな、
クラヴィアさんを頼っちゃうのよ」
[リート]「そうですね……」
クラヴィアさんはあまり自分の話をしない。
[リート](私は、いつもクラヴィアさんに助けられて、
いろいろ教えてもらってばかりだけど……)
そうするとクラヴィアさんは、
一体誰を頼るのだろう。
そんなことを考えていると、
ビアンカさんがこそっと耳打ちをしてきた。
[ビアンカ]「ライバルが多くて、大変だと思うけど、
頑張ってね」
[リート]「え?
い、いえ、私は、その──」

[クラヴィア]「あなたは、年越し蕎麦って知っていますか?
年はすっかり明けてしまいましたが……」
[リート]「……すー……」
[クラヴィア]「あ……」
[クラヴィア]「眠ってしまいましたか……」
彼女はこたつに突っ伏して、
気持ちよさそうに眠っていた。
[ソプラノ]「ふごごご……」
見ると、
頭から落ちたソプラノが
こたつに突っ伏した彼女の顔を塞いでいる。
[リート]「うぐぐぐ……」
苦しげな呻きを漏らしている。
[クラヴィア]「……おやおや、仲が良いのは結構ですが、
これじゃ、苦しいですよね」
ソプラノをそっと抱き上げ、
クッションに移動させる。
眠っている彼女の髪に、そっと触れる。
[クラヴィア]「今日も一日お疲れ様でした」
[クラヴィア]「あなたが楽団に来てくれてから……
一日が経つのが、あっという間な気がします」
[クラヴィア]「私がいなくても……
大丈夫ですよね」
[クラヴィア]「もう二度と、ここに、
間違った歴史が産まれて来ることは──」

やっと私は、クラヴィアさんにベッドへ
押し倒されたのだと理解する。
で、でも、甘い雰囲気なんて微塵もない。
[クラヴィア]「『私』は、あなたが、好き」
[リート]「──」
[クラヴィア]「そうでしたね」
[リート]「え、あ、あの──」
[リート]「ッ──」
クラヴィアさんの顔が近づいてくる。
いつもの穏やかで柔らかな眼差しは
感じられない。
私は息が止まりそうになる。
どうしてこんなに苦しいの……?
[クラヴィア]「でしたら、さっさと処理してもらいましょう」
[リート]「……クラヴィアさん……」
もう、距離なんてほとんどない。
互いの熱を感じられるほど近くにいる。
私の耳に、温かいものが触れる。
熱く濡れた感触に、舐められたのだと
思考がようやく追いつく。
まさか、こんなこと、
クラヴィアさんがするなんて……。
[リート]「ッ──」
[リート]「あ、や……」
[クラヴィア]「どうして?」
[リート]「……っ、だって……」
このままじゃ、思考が麻痺する。
だめだ、もう自分が今どうなっているかも
わからない。
[クラヴィア]「面倒だな……。
自分で、お願いします」
[クラヴィア]「服を、脱いでください」

[リート]「きゃッ」
何かにぶつかって転びそうになったところを、
誰かの腕が私の身体を抱き留めている。
慌ててお礼を言おうと見上げると、
黒いフードを被った男の人だった。
[リート]「……?」
どうしてだろう、胸の中でざわざわと
不思議な感覚がする。
なぜか、あの泣き声とこの人の顔が重なった。
[リート](なんで……?
この人は誰なんだろう……?)
[リート](……って、ボーッとしてる場合じゃなかった!)
私が体勢を戻すと、その人はすぐに手を離す。
そして無言のままきびすを返して立ち去ろうとする。
[リート]「あ…あのッ!」
声をかけると、一瞬だけ足をとめてくれた。
[リート]「ありがとうございました」
しっかりと頭を下げて感謝を伝える。
[忘却の使徒]「……あ?」
私はそれだけ伝えて、
劇場への道をまた歩き出す。
[忘却の使徒]「……」
[忘却の使徒]「何を、言った……?
あの女……」

使徒さんは仕方なげにもう一度腰を下ろす。
つかの間、私達は羽を休める。
使徒さんは目を閉じて、私の話を聞いている。
[リート]「私はそこの孤児院で育ちました。
ここにいるシスターや、子供たちが私の家族」
[リート]「シスターイヴァンは、
シスターなのにちょっとやんちゃなところが
あるんです」
[リート]「子供達だけで大騒ぎなのに、
それにシスターも加わっちゃような人で……」
[リート]「いつも楽しい音で溢れてました。
でも、今は何も聞こえない……」
[忘却の使徒]「……そうか」
[忘却の使徒]「何も聞こえないのと、
余計なものばかり聞こえるの、
どっちがいいんだろうな」
[忘却の使徒]「俺には、
お前が、どう生きてきたかなんてわからねぇし、
家族が、どんなものかもわからねぇ」
[忘却の使徒]「でも……」
[リート](私は、この人のことをどう思っているんだろう)
[リート](わからない……。
一言では言い表せない複雑な感情がある)
[リート](でも、こうして一緒にいると、
なぜか落ち着くような気がする)
[リート](まるで、家族と一緒にいるときのような……。
どこか懐かしい、不思議な感じだ)
[リート](冷たい雨に降られているのに、
触れている部分だけやけに温かい)
妙にその熱を意識してしまって、
自分の顔が熱くなるのを感じた。
[忘却の使徒]「温かいな……」
[忘却の使徒]「こんなに、温かいものなのか……」
[忘却の使徒]「知らなかった……。
誰かと触れ合ったことなんて、
今まで、なかったから……」
[忘却の使徒]「……悪くない、気分だ……」
[忘却の使徒]「家族……。
家族も、こんな風に、温か、い……」

彼の瞳から一筋の涙が落ちる。
[リート]「私の音、届いていますか?」
私は唇でその涙をすくう。
吐息を漏らした唇に、自然と唇を重ねていた。
[忘却の使徒]「……どうしたらいいか、わからないんだ……」
[忘却の使徒]「身体の中から、なんかがこみ上げてきて、
苦しくて……」
[忘却の使徒]「胸ん中が、熱くて、喉が焼けるようで、
でも、何かが出て来ようと暴れてやがる……」
それは『情熱』だと、私はわかる。
[リート]「音楽にしてみては、どうでしょうか」
[忘却の使徒]「俺は楽器なんて持ってない、演奏だって──」
[リート]「歌えば、いいと思います」
[忘却の使徒]「歌えない。俺の声は雑音だ」
[リート]「あれ、知らないんですか?
あなたの声って、とても素敵なんですよ」
[ソプラノ]「ま、俺様の美声には劣るがな……むぎゃっ」
とりあえず、ソプラノの嘴を掴む。
[リート]「聞いていると、胸が苦しくなるのに……、
甘く愛しい気持ちになるんです」
[ソプラノ]「人はそれを恋と呼ぶ……むぎゅぎゅ」
[忘却の使徒]「……歌って、いいのか?」
[リート]「はい。
私は、あなたの音楽が聞きたい」
[忘却の使徒]「…………ッ」
戸惑いながらも、
彼は音を紡ぎ始める。
最初は聞こえないくらいの小さな音、
掠れた声。
でも、徐々に歌になっていく。
※文章および画像は開発中のものです